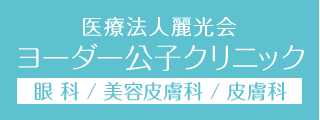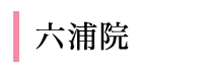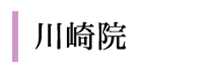診療内容
ニキビ
ニキビは90%以上の人が経験する身近な病気です。特に思春期にできることが多いため、「青春のシンボル」、「成長過程の一つ」というとらえ方をされがちですが、炎症がひどいと痕が残ることもあり、患者さんにとっては大きな苦痛です。これまでは、軽症のうちは化粧品やスキンケアだけで対応し、症状がひどくなったら医療機関(病院、医院)にかかるというのが一般的でしたが、最近治療法が進んで早期の症状から医療機関で治療できるようになりました。
症状
皮脂(皮膚のあぶら)の分泌が多いことと毛穴の先が詰まることで、毛穴の中に皮脂がたまることで始まります。この状態が面皰(めんぽう)です。面皰の中は、皮脂が豊富で酸素が少なくアクネ菌(Propionibacterium acnes)が増えやすい環境にあります。アクネ菌はどんな毛穴にもいる常在菌ですが、数が増えると炎症を起こして赤いぶつぶつしたニキビや膿がたまったニキビを引き起こします。強い炎症を生じて、毛穴の周りの皮膚に障害を与えると、ケロイド状に盛り上がったり凹んだりして瘢痕(はんこん)を残します。
大人のニキビ
大人になってもニキビの症状が続いたり、大人になって初めてニキビができる人もいます。このようなニキビが「大人のニキビ」といいます。
大人のニキビの発症メカニズムは思春期のニキビと同じですが、女性に多く、ストレスや睡眠不足、生活の不規則、不適切なスキンケアなどが要因となる場合があります。
また、思春期と比べると乾燥肌の方が多いため、治療の副作用軽減のために保湿剤が必要になる場合があります。
治療法
塗り薬や飲み薬での治療が一般的ですが、当院では、その他にも美容皮膚科との連携でレーザー治療やケミカルピーリング、医療機関のみで処方できる医薬品や漢方の取り扱いもあります。患者様のお悩みやご要望にそった治療をご提案いたします。お気軽にご相談ください。
粉瘤
粉瘤(ふんりゅう)とは皮膚の良性腫瘍の1つです。表皮嚢腫(ひょうひのうしゅ)はアテローム、アテローマとも呼ばれており、表皮でできた袋のような腫瘍です。
皮膚の下に袋状の構造物ができ、本来皮膚から剥げ落ちるはずの垢(角質)と皮膚の脂(皮脂)が、剥げ落ちずに袋の中にたまってしまってできた腫瘍の総称です。
治療
強い炎症を伴う場合はすみやかに切開して、膿みを出しますが、特に赤みや痛みを伴わない場合は、外科的切除手術(メスを使ってアテロームを表面の皮膚ごと切り取って縫ってしまう)をすることになります。巨大なものでなければ、局所麻酔の日帰り手術が可能です。
良性腫瘍ですので、切除しなくても構いません。しかし、放っておくと、炎症を起こしたり、非常に大きくなったりするものもあるので、ある程度以上の大きさになったものは切除したほうがよいでしょう。
皮下皮膚腫瘍
皮膚にできるしこり(皮膚腫瘍)、皮膚の下にできるしこり(皮下腫瘍)をいいます。
主な疾患は、色素性母斑、脂腺母斑、リンパ管腫、脂肪腫、粉瘤(アテローム)、石灰化上皮腫、汗管腫、稗粒腫(ひりゅうしゅ)、軟線維腫、尋常性疣贅(イボ)、太田母斑(青いあざ)、血管腫(赤いあざ)など多数あります。
治療
疾患の種類、性質、大きさに応じて様々な治療法のなかから選択して治療します。小さなものは、炭酸ガスレーザーや電気メスで焼く方法、切除後縫合する方法などできる限り傷が残らない、目立たないように配慮した治療方法をご提案いたします。
アトピー性皮膚炎
かゆみを伴い慢性的に経過する皮膚炎(湿疹)ですが、もともとアレルギーを起こしやすい体質の人や、皮膚のバリア機能が弱い人に多く見られる皮膚の炎症を伴う病気です。
湿疹の特徴
◎赤みがある、じゅくじゅくして引っかくと液体が出てくる、ささくれだって皮がむける、長引くとごわごわ硬くなって盛り上がる
◎左右対称にできることが多い
◎おでこ、目のまわり、口のまわり、耳のまわり、首、ワキ、手足の関節の内側などに出やすい
原因
炎症は、本来は体の外から侵入してきた敵を退治する免疫反応によって起こるもので、細菌やウイルスなどから身を守るために必須のものです。しかし、アトピー性皮膚炎ではこの免疫が過剰に反応し、本来退治する必要のないものに対しても不必要に炎症が起きてしまうことが病気の根本にあります。
もともとのアレルギーを起こしやすい体質や皮膚のバリア機能低下も大きく関係しますが、その他、長期に渡る皮膚への強い刺激やストレス、疲労なども免疫を不安定にしてアトピー性皮膚炎を悪化させることがあります。
治療
アトピー性皮膚炎に対する治療は、薬物療法によって皮膚の炎症を抑えることが基本になります。薬物療法には、ステロイド外用薬、非ステロイド外用薬、タクロリムス軟膏(免疫抑制剤)、保湿外用薬、抗アレルギー薬などの内服が用いられ、症状により、それぞれ単独で、または組み合わせて使用します。
当院では、アレルギー反応を起こしにくくする効果が期待できる『ヒスタグロビン+ノイロトロピン』を定期的に注射する治療も対応しています。
※ヒスタグロビン注射を受けるためには、アレルギーの血液検査V39が必要です。1週間後に結果が出ますが、その結果次第でヒスタグロビン注射が適用になるかどうか医師が判断いたします。また他院で受けられた血液検査の結果(1年以内)をお持ちになっていただき、適用の場合は、当日から注射可能です。(3割負担 5,000円程度)
かぶれ
かぶれ(接触皮膚炎)とは外来性の刺激物質や抗原(低分子の抗原であるハプテン)が皮膚に接触することによって発症する湿疹性の炎症反応をいいます。かゆみやヒリヒリ感が伴い、赤くなったり、ぶつぶつができたりする皮膚疾患です。
大きく刺激性とアレルギー性に分類されます。
治療と予防
問診や視診、触診、パッチテストによって診断を行い、接触皮膚炎の治療で最も大切なことは原因となるアレルゲン、接触刺激因子を見つけ出し除去することです。皮膚炎やかゆみを抑えるためにステロイド外用薬での治療が一般的ですが、かゆみが強い場合は抗ヒスタミン薬の内服薬を処方される場合もあります。
乾燥肌
乾燥肌とは、皮膚の角層と呼ばれる部分の水分量が低下して、肌が乾燥した状態をいいます。皮膚のつっぱり感やかさつき、粉吹き、かゆみなどの症状がみられます。皮膚のバリア機能が低下することで、しばしばかゆみを伴います。
原因
加齢に加え、空気の乾燥や寒冷、摩擦などの刺激、紫外線の影響、洗いすぎなど、様々な要因が絡み合って起こります。角層(皮膚表面の細胞層)で、肌の潤いに重要な役割を果たす「天然保湿因子」(アミノ酸や尿素など)、セラミドなどの「細胞間脂質」、皮膚の表面を覆って乾燥を防ぐ「皮脂」の分泌は、個人差はありますが加齢とともに減少していきます。
治療
日頃から適切なスキンケアを行うことが大切です。保湿剤は添加物が少なく、使用感の良い長期的に使いやすいものを選びましょう。
やけど
治療
まずはあわてずに水道水などで患部を冷却し、できるだけ冷却しながらご来院いただき、症状の深度によって外用薬を使い分けます。また、場合によっては抗菌剤や内服薬を使用する場合があります。
ウオノメ・タコ
タコは足の裏以外にも、生活習慣や職業やその人の癖などにより、身体のあちこちにできます。タコに痛みや赤みを伴う場合は、細菌感染を起こしている可能性がありますので早めに皮膚科を受診して下さい。特に糖尿病の患者さんでは重症化し易いので注意が必要です。
治療
治療の根本は原因である「皮膚の一部が圧迫などの刺激を受け易い」状況の改善です。当院では液体窒素による治療も行っております。
水虫
水虫とは、白癬菌(はくせんきん)というカビが皮膚に感染する病気です。日本人の5人に1人が水虫にかかっているともいわれており、非常に身近な病気です。水虫がいるかどうか、皮膚や爪の一部をとって、白癬菌がいるかどうか検査し診断します。
治療
塗り薬が中心となります。直接薬を塗ることにより、白癬菌を殺したり、白癬菌の成長を抑えることができます。
単純ヘルペス(口唇ヘルペス)
くちびるやその周囲に小さな水ぶくれができます。単純ヘルペスウイルスというウイルスに感染することで起こる病気です。直接的な接触のほかにウイルスがついたタオルや食器などを介しても感染しますので、家族間での感染が多いです。再感染や再発を繰り返すことが特徴で、大人に見られる口唇ヘルペスのほとんどは再発です。
原因
初感染の後、ヘルペスの症状がおさまっても、ウイルスはいなくなったわけではありません。現在使える薬では潜伏しているヘルペスウイルスを退治することはできません。再発でヘルペスの症状が現れやすいのは、疲労や風邪、紫外線、胃腸障害、ストレスなどの免疫力の低下などの場合です。
治療
抗ヘルペスウイルス外用薬や内服抗ヘルペスウイルス薬で治療します。抗ヘルペスウイルス薬は症状が出たら、できるだけ早い時期に治療を始めるのが望ましいとされます。
帯状疱疹
皮膚の内側のピリピリとした痛みと、痛みに沿って帯状に赤み・ブツブツ・水ぶくれができる病気です。右腕だけ、左半身だけというふうに体の片側に起きることも特徴の一つです。子どものころにかかることの多い「水ぼうそう」のウイルスが原因で起こります。水ぼうそうのウイルスは、完治後も体内の神経節というところに潜んでいます。過労や加齢、病気などで免疫力が低下すると、神経を傷つけながらその神経の流れに沿って帯状の皮膚炎を起こします。
治療
治療は主に、ウイルスの増殖を抑える薬の内服です。顔面にできたものや痛みが強いときなどは入院して点滴で治療することもあります。薬による治療を早く始めることが大切です。
ホクロ・イボ
ホクロの医学的な病名は、“母斑細胞性母斑”で、良性の腫瘍の仲間に入ります。腫瘍は、細胞が増殖していくため、徐々に大きくなります。
「イボ」は、皮膚から盛り上がってできたものの総称です。
治療
ホクロは、炭酸ガスレーザーで病変をとる方法や切除する方法などがあります。イボは、液体窒素による治療や内服薬での治療方法があります。当院でも、液体窒素による治療を行っています。
乾癬
乾癬は炎症性角化症に分類される、慢性の皮膚疾患です。経過が長く、完治が難しい皮膚疾患でもあります。乾癬はまれな病気でなく誰にでも起こりうる疾患です。乾癬は頭や顔、体や手足など、全身どこの皮膚にでも発症します。
原因
乾癬の原因はまだわかっていません。
しかしながら、もともと生まれつき乾癬を発症しやすい素因を持つ人に、ストレスや生活習慣や食習慣・感染症などの何らかの発症要因が加わって、発症すると考えられています。
治療
外用療法・・・皮疹が体の広範囲に及ぶことが多く、また頭や顔、体や手足など、皮膚の厚さの異なるあちこちの部位に見られるため、場所によって外用薬を使い分ける必要があります。
内服治療・・・かゆみを軽減し炎症を抑えるために、外用薬と併用して抗アレルギー薬が内服処方されることがあります。その他、自己免疫抑制剤などの内服が使用されることもあります。
水イボ
伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)ともいわれ、伝染性軟属腫ウイルス(MCV)の感染により生じます。接触感染し、皮膚に微小なキズがあった場合にMCVが体内に侵入して皮膚の角化細胞に感染を生じます。MCVに感染した角化細胞は膨脹し、分裂速度が速まって、軟属腫小体と呼ばれる細胞の塊を形成します。これが症状としてのイボとなります。
症状
主に小児の体幹や四肢に粟粒大~数mmまでの光沢のあるイボができ、徐々に数が増えてきます。プールなどで肌の接触により感染しますので、最初は子供同士で触れ合う場所に水イボはできます。イボを触った手で他の場所を引っ掻くなどして、皮膚の表面で感染は拡がることが多いです。何もしなくても自然治癒することがほとんどですが、肌の弱いお子様(特にアトピ―性皮膚炎のある子供)の場合、極端にたくさんの水イボができて難治化する場合もあります。状況に応じて治療を行ってまいります。
治療
【ピンセットで除去する方法】数が少ない場合は、ピンセットで摘みとります。ただ、小さなお子様の場合、痛がる場合があります。
【液体窒素による凍結療法】液体窒素により、イボを凍結させる方法があります。
【内服・外用薬による治療】痛みがないのが利点です。
シミ・炎症性色素沈着
原因は、メラニンの増加によるものです。メラニンは肌に色味を与え、有害な紫外線のダメージから肌を守ってくれる成分です。しかし、紫外線を多く浴びたり、妊娠やホルモンバランスの崩れ、肌の傷、ニキビや加齢などが原因で過剰に生成されるとシミの原因になります。
また、シミと一言でいっても、様々なタイプのものが含まれています。
種類
- 老人性色素斑
もっとも一般的に見られる代表的なシミです。 紫外線による皮膚のダメージが主な原因で、長年日光に暴露されてきた顔面や腕、手の甲などにできます。「老人性…」と病名には付いていますが、必ずしも高齢者だけに見られるわけでなく、早い人では20歳台で症状が現われることもあります。
- 炎症性色素沈着
色素沈着はシミと違って時間の経過とともに自然に色が消えていきます。 色素沈着を早く消すためには、各種美白剤の内服・外用療法を行ないます。
- 肝斑 ( かんぱん )
女性に多い、両ほほに左右対称性に広がるシミです。 妊娠・出産をきっかけに現われることがあります。また、日光に当たると悪化するので、夏になると色が濃くなる傾向があります。過労やストレス、ある種の薬剤(経口避妊薬、抗てんかん薬などの一部)も症状を悪くする要因です。
治療
レーザー治療の他、当院では、漢方薬や内服薬を適切に組み合わせた治療を行っております。症状に応じて最適な治療方法をご提案させていただきます。
湿疹
湿疹は様々なものが原因となって起こる皮膚の炎症です。湿疹には接触性皮膚炎というアレルギー反応や皮脂の分泌過剰が原因で起こる脂漏性皮膚炎など様々なことが原因で発症します。湿疹の原因を適切に把握することで正しい治療につながっていきます。皮膚の状態把握をしっかりと行い、それぞれの原因に応じた治療が大切です。
湿疹を放置してしまうと、再発を繰り返したり病態の悪化につながる場合があります。
種類
以下のような代表的な種類があります。
- アトピー性皮膚炎
- 接触性皮膚炎
- 尋常性湿疹(手湿疹)
- 脂漏性湿疹
- 皮脂欠乏性湿疹
- 汗疹性湿疹(かんしんせいしっしん)
治療
湿疹の状態にあわせて治療します。頭、顔、体、陰部、手、足など皮膚の厚さが違いますので、皮膚の状態にあわせた薬を使用することが大切です。 皮膚の乾燥があれば、皮膚の状態にあわせて保湿剤を使用します。 かゆみがあれば、ステロイドの塗り薬やかゆみ止めの塗り薬や、抗アレルギー剤の飲み薬を使用します。
掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)
手のひらや足のうらに、うみをもった小さな水ぶくれ(膿疱)がくり返しできる病気です。膿疱の中には細菌やウイルスなどの病原体は入っていないため[無菌性膿疱(むきんせいのうほう)]、直接触れても人に感染することはありません。
症状
主に、手のひらと足のうらに、水疱や膿疱などの病変があらわれます。手のひらや足のうら以外にも、すねや膝、肘、頭などに症状があらわれることがあります。爪が変形したり、骨や関節が痛んだりする場合もあります。できはじめにかゆみを伴うことが多く、しばらくすると膿疱が乾いて茶色っぽいかさぶたとなり、はがれ落ち、角層がつみ重なって厚くなると、歩くたびにひび割れて痛みを生じるようになります。関節や骨そのものに炎症が起きて激しい痛みを伴う例もあり、特に胸骨と鎖骨の接合部などに起こることが多いです。さらに首や肩、腰など痛みが広範囲になることもあります。
治療
掌蹠膿疱症の治療について、明確な治療指針は現在のところありませんが、原因と考えられる要因を検討し、患者様ごとの症状に合わせて治療を行います。金属アレルギーや病巣感染や喫煙など、悪化因子がわかっている場合には取り除くようにします。もし、これらの増悪因子がみつからない場合は、対症療法を行ない、まず外用療法を選択します。皮疹が頑固な場合は紫外線療法や短期間のビタミンA誘導体の内服を行うこともあります。
毛孔性苔癬(もうこうせいたいせん)
毛孔性苔癬とは、皮膚の毛穴に、角化した粟粒ほどの大きさの発疹がたくさんできる皮膚疾患のことです。
ザラザラした感触が特徴的で「さめ肌」と呼ばれることもあります。
発生する箇所は、主に二の腕ですが、太ももや肩、背中などにも発生することがあります。
発生時期は、5~6歳の小学校に入学する頃を始めとして、思春期に最も目立つようになるのが一般的ですが、その後、加齢とともに自然と落ち着いていく傾向があります。
症状
発疹は触るとザラザラとした感触ですが、痛みや痒みなどの自覚症状を伴うことはまずありません。発疹が起こっている毛穴は開がって大きくなり、その中には角栓が詰まっています。
発疹の大きさは、およそ1~3mmです。さらに、赤みのある発疹を伴ったり色素沈着して肌が黒ずんだりすることもあります。
治療
毛孔性苔癬は、一定の期間を経て自然と無くなっていくのが一般的ですが、数年以上続くことも多い疾患です。しっかりと積極的に治療を行いたい方は、自費診療になりますが、レーザー治療(ピコフラクショナル)もございます。
詳しくはお問い合わせください。